最近読んだ本。ノンフィクション。
福島第二原発の奇跡。高嶋哲夫著。PHP研究所 2016年刊行。
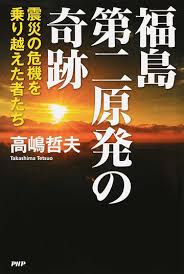
高嶋さんは、小説家で、クライシスノベルというんでしょか、巨大地震や火山噴火などをモチーフにリアルなストーリーをつむぐ方。高嶋さんのある小説~首都崩壊~を読んだことがきっかけで、高嶋さんがもと原発技術者であり、東日本大震災当時、1エフ~福島第一原発~だけでなく、実は2エフ、福島第二原発も相当深刻な状況だったことを取材し本書であきらかにしていたにことを知りました。
前のエントリーでも書きましたが、フクシマ50という映画が公開されたから…というわけではないのですが、五輪が終われば、わたしたち日本人は、2021年ーーあれから10年の節目の年を迎えます。
当時、あんなに心配し、多少なりともほんろうされ、いきどおり、語られ尽くされた感のあるフクシマや原発ですが、どうも自分のなかで全体像をつかみきれていない、大事なところを忘れてしまった感覚があり、映画公開とは関係なく、ちょっと自分なりに、何かしら読んでみたいな、と思っているところで出会った本でした。
当時、全国、全世界の視線が第一に集まるなか、実は第二でも同じくらい危機的な事態が進行していたことを、恥ずかしながら、まったく私は知りませんでした。
第二でも、所長以下、運転員や復旧の皆さんがメルトダウンを起こさぬよう、できるだけベントをしないよう、不眠不休で必死の努力を続けられていた。第一と第二の結果を分けたのは、ただ奇跡、偶然でしかなかったように思えます。第一と第二は20キロほど離れた同じ沿岸にあり、ともに4基の原子炉を抱え、第二の建設は第一の10年後。双子のような関係です。
何が命運をわけたか。
第一では、巨大地震により、冷却系への外部からの電源供給がすべて断たれたのに比べ、第二では、かろうじて1系統だけ外部からの電源供給が生きていた。ほかにも細かい差がありますが、それが最も大きかった。逆に言うと、第一でも、まったくの全電源喪失にならず、1系統でも電力が届いていたらまったく違った展開だったのでしょう。実際にはすべての電源供給がたたれ、手足をもぎとられたような条件下で、第一のみなさんは、吉田所長以下、非常に厳しいたたかいを強いられた。本のなかで、第二でも深刻な状況が次々と展開してゆく。その状況を読み進みながら、あたまの片隅で第一の過酷さを心配する…そんな読み方になりました。
具体的には、第二でも、外部電源がかろうじて1系統だけ残ったとはいえ、第一と同じように巨大津波に襲われ、冷却系の施設は水没、資材がまんぞくに届かないなか、格納容器内の圧力上昇と水温上層のコントロールに神経をすり減らす展開が続く。さらに、そのうちに第一で水素爆発が起き、第二は、第一の放射性物質が飛散してくるなか、第一のスタッフのフォローも担うという難しい役割もあった。
知らなかったことがあまりに多く、不明を恥じるばかりです。
知らなかった事実が目白押しで蒙を啓かれる思いで読みましたが、ただ、作品としては、冷却にいたるまでの様子を各人からの視点で同時並行的に描いたためか、何を目指しての作業なのかについての繰り返しが多く、やや読みにくく感じる部分も。
小説は、ストーリテラ―が自在に脳内でドラマチックに編集もできるでしょうが、現実はそうではない。主要な人物から聞き書きした事実をどう削り、時系列にどうまとめ山場を設定するか。すこし難しいところもあるのでしょうね。貴重な証言の数々なので、多少の重複感は犠牲にしたのかもしれませんが、編集者ががんばってほしかったところかな。
ことしで9年。来年は10年。
節目の年に、当時は語られなかった真実に、改めて光が当たるといいなと思います。原発は推進、反対、いろいろな意見、評価があると思いますが、まずは同じ事実を踏まえることが必要なんじゃないかなと、私は思います。